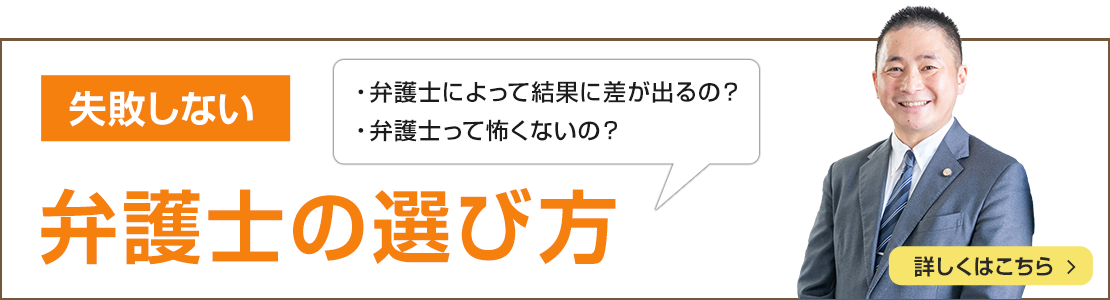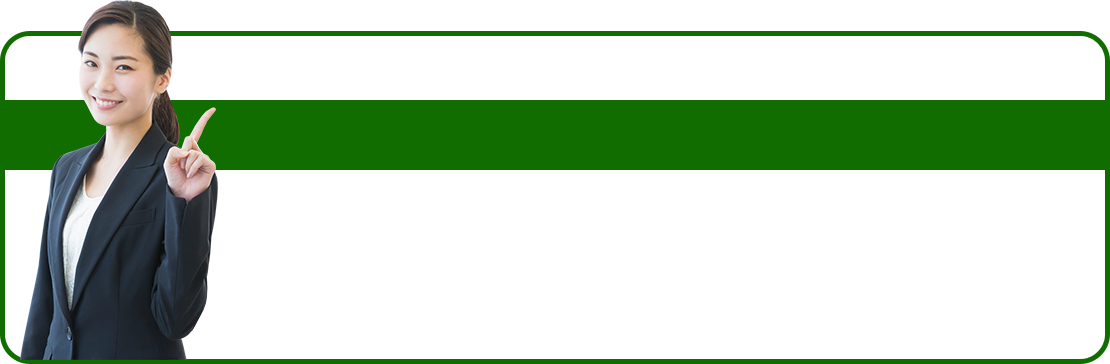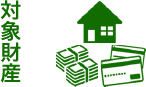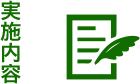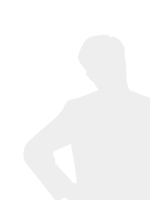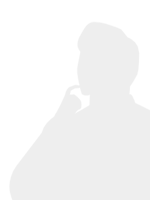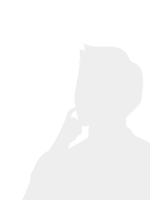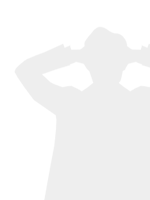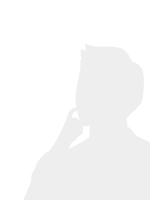遺産分割協議とは? 協議の方法やもめてしまった場合の対処について弁護士が解説
目次
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産について、相続人全員で「誰が・何を・どのように取得するか」を話し合いで決める手続きをいいます。
遺産分割協は、相続人全員の合意があってはじめて成立します。
一人でも相続人の合意が得られないと成立しません。
合意ができない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判に進むことになります。
遺産分割協議が必要なケース
遺産分割協議が必要となるのは、相続人が2名以上いる場合で、有効な遺言がない場合、または相続人全員が合意のうえで遺言の内容どおりにしないと決めた場合です。
遺言は原則として協議より優先されますが、相続人全員(受遺者を含む)が一致して遺言と異なる内容にすることも可能です。
なお、遺言に記載のない財産がある場合は、その部分だけ遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議が不要なケース
相続人が1人しかいない場合
相続人となるはずの全員が相続放棄した場合、または全員が相続人から除外された場合
有効な遺言に従って分ける場合
遺産分割協議のメリット
最大のメリットは、全員の納得感を得やすいことです。合意がなければ成立しないため、話し合いを重ねることで、結果として受け入れやすい分け方に到達しやすくなります。
遺産分割協議をしない場合のリスク
適時に処分できないリスク
協議が終わるまで遺産は相続人の共有です。適切な時期に売却などができないリスクがあります。
相続関係が複雑化するリスク
協議しないまま相続人の一部が亡くなると、さらに相続が発生し、関係者が増加して手続きが難しくなります。
遺産分割協議は誰が参加する?
協議は相続人全員の合意があって成立します。
したがって、参加者は相続人全員です。
一人でも相続人が欠けると無効となります。
相続人の範囲と調査
相続人の一人でも欠けると遺産分割協議が無効になるため。誰が相続人かを正確に確定する必要があります。
相続人は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などが含まれ、民法上の優先順位に従って定めます。
また、先に亡くなっている相続人がいる場合や、被相続人が相続人となる遺産分割協議が未了の場合などの数次相続が発生している場合は、相続人の確定がさらに複雑になります。
相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を収集する必要があります。
金融機関で求められることもありますし、戸籍の収集は必須です。
戸籍の調査による漏れのない相続人調査がまずは重要です。
意思能力がない相続人がいる場合
認知症などで協議内容を理解・判断できない相続人がいる場合、遺産分割協議が進められません。
その場合、成年後見人などの法定代理人を選任し、代理人を通じて協議を行う必要があります。
遺産分割協議の進め方
相続人を確定する(相続人の調査)
戸籍一式を収集し、漏れなく正確に特定します。
遺産をもれなく調査する
不動産・預貯金・株式・動産等のプラス財産だけでなく、借金・住宅ローン等のマイナス財産も含め、調査が必要です。
遺産を適切に評価する
公平な分割の前提として金銭評価を行います。
不動産や非上場株式など評価が難しい財産もあります。
遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
相続人全員で協議し、必要に応じて特別受益・寄与分の主張を整理します。
遺産分割協議は、相続人全員で合意して成立させる必要があります。
適切な遺産分割協議書を作成する
成立後は速やかに協議書を作成します。
名義変更や相続税手続で提出を求められる場合があるため、早めの作成が有益です。
なお、手続等で実印と印鑑登録証明書の添付が必要となることが多いです。
遺産分割協議を円滑に進めるためのポイント
財産目録の作成
プラス・マイナスの財産を一覧化し、協議書添付や相続税申告にも活用します。内容の共通理解に役立ち、手続がスムーズになります。
証拠資料の開示
管理中の財産については、残高証明書などの客観資料もあわせて共有し、不信感や誤解を避けるようにします。
法定相続分をベースに協議
法定相続分を出発点にすることで、公平感を得やすく、合意形成が進みやすくなります。
他の相続人の意向を把握
全員合意が必要なため、希望や理由を相互に確認しながら進めます。対面に限らず、メール・書面・電話・オンラインでも協議可能です。
遺産分割の方法
主に4つの方法があります。一般には「現物分割」をまず検討し、難しい場合は他の方法を順に検討します。
現物分割
財産をそのままの形で各相続人が取得。
メリット
形を変えずに承継でき、売却や精算の手間・費用を抑えられます。
デメリット
財産の数や価値に偏りがあると公平に配分しにくい場合があります。
代償分割
特定の相続人が現物を取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法。
メリット
現物を維持しながら公平な調整が可能。
デメリット
取得者に資金力が必要で、支払いをめぐる紛争の可能性があります。
換価分割
財産を売却等で金銭化して分ける方法。
メリット
金銭にすることで分けやすくなります。
デメリット
売却までの時間・労力・費用(売却費用・税金等)がかかり、財産自体は手放すことになります。
共有分割
財産の全部または一部を複数人で共有する方法。
メリット
財産を手放さず、持分に応じて平等に保有できます。
デメリット
権利関係が複雑化し、処分・管理で対立が生じやすく、将来の手続が重くなりがちです。一般には他の方法が難しい場合の選択肢です。
遺産分割協議のやり直し
いったん成立した協議は、原則としてやり直し不可です。
ただし、次のような場合は例外的にやり直しが可能です。
相続人全員がやり直しに合意
全員一致で合意解除し、再度協議できます。1人でも反対があれば不可です。
協議が無効・取消しとなる事情がある
無効の例
意思能力の欠如/相続人が1人でも欠けていた/相続人でない者が参加していた 等。
取消しの例
重大な錯誤/詐欺/強迫 等。
個別事情により結論が分かれるため、該当の可能性があれば専門家に相談してください。
遺産分割協議でしてはいけないこと
相続人を調査しない
後日未把握の相続人が判明すると、協議が無効となるおそれがあります。
遺産を開示しない
一部の相続人だけに情報を伝える・開示しない対応は、不信感や対立を招きます。全員に公平に開示しましょう。
調査が不十分
対象外の遺産や負債が後から見つかると、追加で協議が必要になります。名寄帳・登記簿、通帳・残高証明、ローン残高証明などを基に丁寧に確認します。
協議書の不備
不備があると金融機関や不動産の名義変更などの手続きができない場合があります。
遺産分割で揉めてしまった場合の対応
弁護士に進行や代理交渉を依頼する
感情的対立が原因で遺産分割協議が行き詰まることは少なくありません。
第三者である弁護士が法的観点から整理し、冷静な協議を促します。根拠の薄い主張には適切な反論を提示し、公平な解決につなげます。
調停・審判より早期解決となるケースもあります。
遺産分割調停を申し立てる
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てます。
通常1〜2か月に1回のペースで複数回行われ、解決まで半年程度〜となることがあります。
合意に至れば調停調書が作成され、不調なら審判へ移行します。
遺産分割の審判
家庭裁判所による判断が審判です。
家庭裁判所が最終的な分け方を決定します。
個別事情を踏まえたうえで、結果として法定相続分に沿う判断となることが多く、不動産が共有となる例も少なくありません。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
専門知識に基づく適切な進行
全体の段取りや留意点を整理し、スムーズに進めることが可能です。
早期解決と負担軽減
期限のある手続にも配慮し、問題が大きくなる前の対応で時間・労力・費用の負担を抑えます。
冷静な交渉と公平な解決
第三者の立場から感情の衝突を調整し、法的根拠に基づく合理的な落としどころを探ります。
依頼者の意向を踏まえた最適解の追求
全体の調和に配慮しつつ、依頼者の意向と法的妥当性を両立させる解決を目指します。
調査・評価・文書作成の支援
不動産や非上場株式の評価、財産調査、財産目録・協議書の作成まで一貫してサポートします。
調停・審判への対応
協議でまとまらない場合も、裁判所手続を適切に代理します。
遺産分割のお悩みは弁護士にご相談ください
不動産を含む相続は、ご自身だけで進めると精神的・時間的負担が大きく、最善の選択肢を見落とすおそれもあります。
相続開始直後や争いになる前の段階からでも、早めに弁護士へ相談することで、早期解決や紛争予防につながります。
遺産分割についてお悩みの方は当事務所にご相談ください。