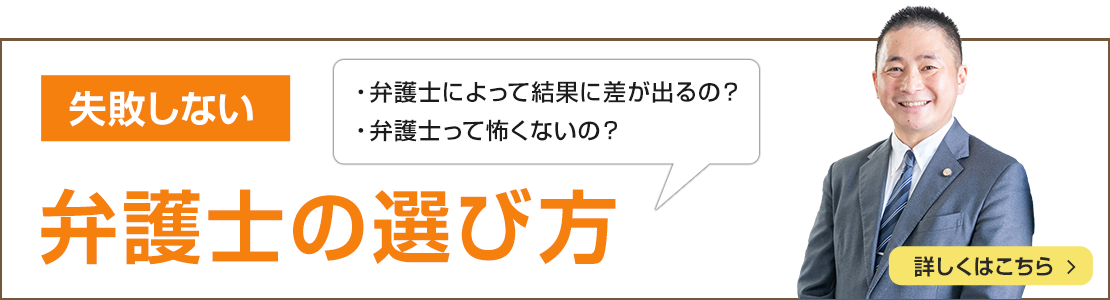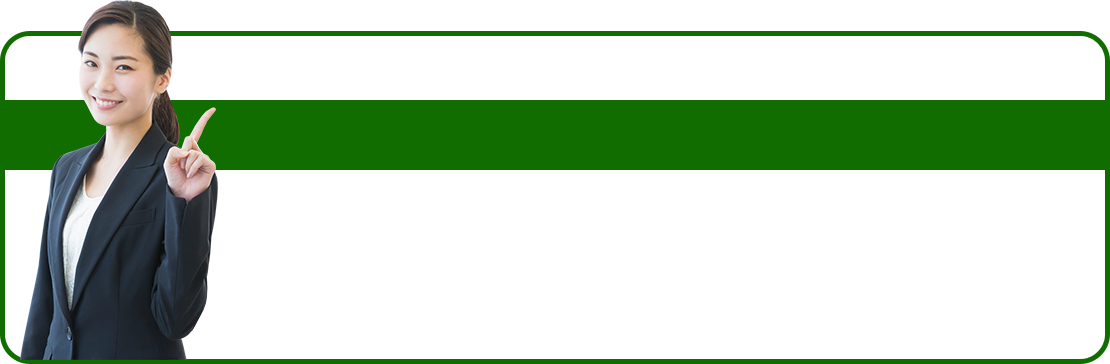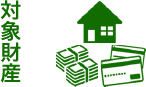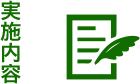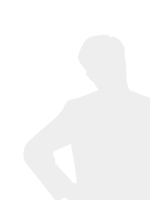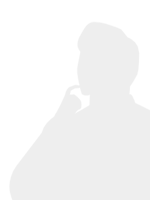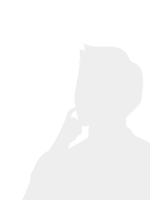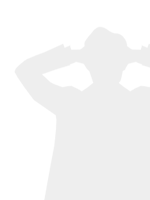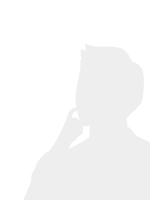不動産による遺留分侵害とその対応を弁護士が解説
目次
遺留分侵害とは?
遺留分とは、配偶者・子・直系尊属などの一定の相続人が、遺言の内容にかかわらず最低限確保できる取り分のことです。
たとえば、相続人が子ども1人だけの場合に、相続人以外の方に遺産のすべてを相続させる遺言を作っていたとしても、相続人であるその子どもには一定の遺留分が認められます。
つまり、遺留分とは、遺言によってもその相続分を奪えないという制度です。
遺言や生前贈与の結果としてこの取り分を下回るときは、不足分の金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。
不動産によって遺留分が侵害される例
たとえば、遺言で「長男に自宅土地建物の全部を相続させる」と指定していたとして、次女に実質的な取り分がない場合、次女は長男に対し不足分の金銭を請求できます。
また、生前に特定の相続人へ不動産を贈与した場合でも、これが他の相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求の対象となり得ます。
不動産が絡む遺留分問題の特徴
金銭での解決が原則
改正民法では、侵害の是正は金銭賠償が原則です。
合意があれば共有化や代償分割など柔軟な解決も可能ですが、原則は金銭での支払いです。
つまり、遺留分の問題を解決するには一定の金銭が必要となります。
評価方法が勝敗を左右
不動産の評価額次第で請求額が大きく変わります。
どの評価を採用するかが最大の争点になりやすいのが実務です。
現金不足のリスク
遺産の大半が不動産で現金が乏しくても、適法な請求には応じる必要があります。
支払えない場合、差押え・競売の可能性もあります。分割払いや期限猶予・担保提供などの支払い条件の交渉も検討する対象となります。
計算と交渉が難しい
基礎財産の確定、生前贈与の扱い、評価選択、反論対応、和解ラインの見極めなど、専門的な判断が不可欠です。
手続の流れ(5ステップ)
請求できる立場か確認
そもそも、遺留分権利者(配偶者・子・直系尊属)であるかの確認が必要です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
また、相続放棄・遺留分放棄、相続欠格・廃除の有無も確認する必要があります。
自分の遺留分割合を把握
相続人の組合せにより遺留分割合は変動します(例:子のみ=1/2、配偶者と子がいる場合など)。
遺留分額(最低限もらえる額)の計算
「遺留分の基礎となる財産」×「個別の遺留分割合」。
基礎財産には、不動産・預貯金等のプラス財産に加え、
相続人への生前贈与(原則相続開始前10年の特別受益)
相続人以外への贈与(原則相続開始前1年。ただし害意ある贈与等は例外)
を考慮し、負債を控除します。ここで不動産評価が最大の争点になります。
侵害額の算定
「自分の遺留分額」−「実際に取得した額」=請求できる不足分。
時効に注意して請求
遺留分侵害額請求権は、侵害を知った時から1年、かつ相続開始から10年で時効消滅します。
まずは協議→まとまらなければ内容証明郵便→調停→不成立なら訴訟という順で進めることになります。
不動産の主な評価方法と選び方
路線価(相続税路線価)
国税庁公表。公示価格の約8割が目安。
固定資産税評価額
自治体算定。公示価格の約7割が目安。
公示価格・基準地価
公的な「正常価格」の指標。個別補正が必要。時価(実勢価格)
相続開始時点に売買されると通常見込まれる価格。不動産会社査定等を活用。
不動産鑑定評価額
鑑定士による専門評価。争点化した場合の有力根拠となりますが、鑑定費用が20〜100万円程度発生するのが一般的です。
戦略の基本
請求する側
取り分最大化のため、高めの評価(時価や査定)が可能なようにすべきです。
請求される側
遺留分による支払額抑制のため、低めの評価(路線価・固定資産税評価)で算定されるように反論していきます。
実務上は、双方主張の中間値で落とす和解も少なくありません。支払い困難な場合は分割・期限猶予・担保設定等の条件交渉も有効です。
また、高知県の場合は、売却困難な不動産も多数存在します。
売却困難地域の場合、特にその地域に沿った不動産価格の算定方法をなるべく有力な根拠(たとえば、近隣の売買価格など)とともに示すべきことになります。
遺留分侵害を「未然に防ぐ」ために
生前からの設計で紛争の芽を小さくできます。
遺言での配慮
遺留分に配慮した配分、代償金条項(不足分を金銭で補填する約束)を明記することを検討。
資金手当て
代償金の原資となる預貯金・保険金の準備、保険受取人の設計。これにより遺留分の紛争が生じたとしても、金銭の支払いで解決できる可能性が高まります。
生前贈与の管理
時期・額・対象の記録化、特別受益の扱いを意識。特に10年以上の長期計画。
弁護士に依頼するメリット
最適な評価方法の選定と請求額の適正化
不動産には「時価」「路線価」「固定資産税評価額」など複数の評価手法があります。
物件の状況や権利関係、手続の見通しを踏まえ、妥当と考えられる評価の当て方を検討します。
これにより、過大・過少の振れを抑え、根拠を示しやすい金額での協議が進めやすくなります。
基礎財産の確定(生前贈与・負債の整理)と証拠化
通帳記録や登記事項、固定資産課税台帳などを基に、対象財産・生前贈与・負債の有無を確認し、計算の前提を整えます。
必要資料を収集・整理しておくことで、後日の争点整理がしやすくなり、手続が比較的円滑に進む可能性があります。
相手方の反論パターンに応じた再計算・再主張
評価時点や評価方法、特別受益の扱いなど想定される論点に合わせ、複数の計算案を用意し、関連法令や裁判例に沿って主張内容を調整します。
これにより、交渉の方向性を共有しやすくなり、合意形成の可能性を高めることが期待されます。
支払条件の交渉(分割・期限猶予・担保)
一括払いが難しい場合には、分割回数や支払期日、遅延時の取扱いなどの条件案を作成します。
必要に応じて担保や保証の設定を検討し、未払いリスクの低減に資する合意書の作成を目指します。
調停・訴訟への対応を一任でき、負担を軽減
申立書・準備書面の作成や期日対応などの手続面を任せることで、依頼者は要点の確認や方針決定に専念しやすくなります。
あわせて、費用対効果や見通しを整理し、複数の選択肢を比較検討するための材料を提供します。
まずはお早めの相談を
不動産が絡む遺留分問題は、評価・計算・交渉のいずれも専門性が高く、対応の遅れは不利益につながりかねません。
「遺言内容に不安がある」「生前贈与が多い」「現金が足りないかもしれない」――こうした段階からのご相談が、紛争の予防と費用対効果の高い解決に直結します。
不動産門でお悩みの際は、当事務所へご相談ください。