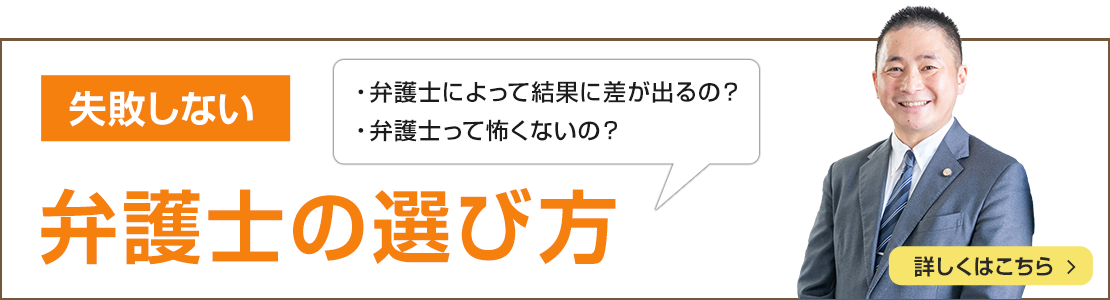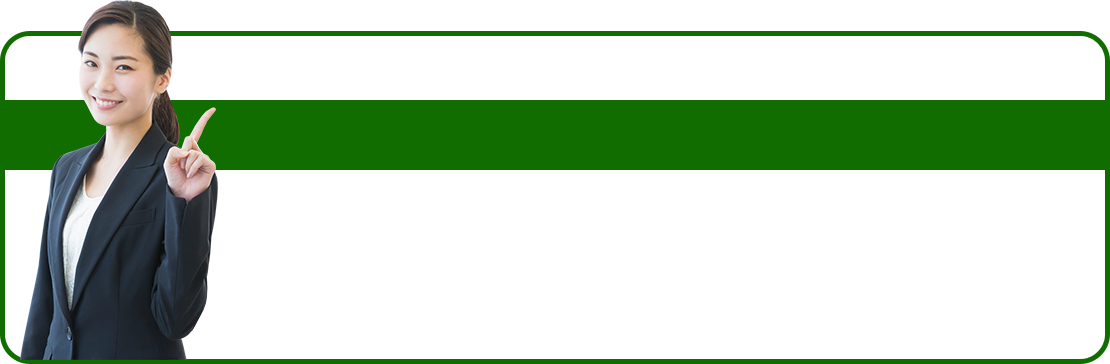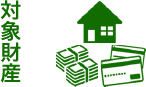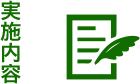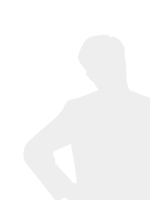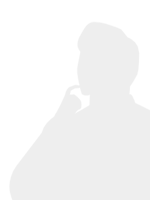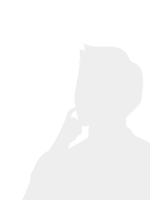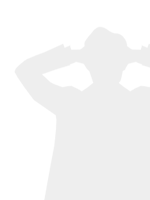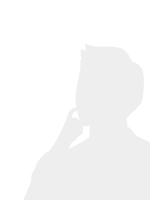遺産分割調停での解決方法と弁護士費用の具体例
遺産分割調停の解決事例と費用
高知市在住のXさん(長女・50代)は、父親が亡くなり、相続人はXさん、弟Yさん、妹Zさんの3人でした。
遺産の概要
不動産
高知市内の自宅不動産(評価額2,400万円)
預貯金(3か所)
四国銀行:600万円
高知銀行:300万円
郵便局:300万円
※合計1,200万円(3人で均等に分けると1人400万円)
父親の生前、弟Yさんは実家に同居していたため、「自宅は自分が引き継ぐべきだ」と主張しました。
長女Xさんと妹Zさんは「不動産も預貯金もすべて3人で均等に分けたい」と考えていましたが、話し合いは平行線のままでした。
弟Yさんは話し合いに応じなかったため、Xさんは当事務所に依頼し、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにしました。
弁護士が行ったこと
①相続関係と遺産の調査(戸籍・登記・預貯金残高証明の取得)
②相続分と分割方法のシミュレーション(売却分割・代償分割)
③調停申立書の作成と提出
④調停期日の出席(代理人として主張・立証)
⑤合意書作成と履行確認(代償金支払い・名義変更サポート)
解決結果
自宅(評価2,400万円)を弟Yさんが取得
代償金としてXさん・Zさんに各800万円を支払い
預貯金(合計1,200万円)は3人で均等に分配(各400万円)
調停申立から合意成立まで約7か月で終了
費用比較
当事務所(本事例の場合)
着手金:33万円(固定)
報酬金:取得額1,200万円 × 11% = 132万円
合計:165万円(税込)
旧弁護士報酬規程(参考)
着手金:(300万円超〜3,000万円以下)= 5% + 9万円
→ 1,200万円 × 5% + 9万円 = 69万円
報酬金:(300万円超〜3,000万円以下)= 10% + 18万円
→ 1,200万円 × 10% + 18万円 = 138万円
合計:207万円(税込)
ポイント
当事務所は旧報酬規程と比べて合計42万円安い料金設定です。
着手金が特に低く、依頼時の初期負担を軽減しています。
報酬割合も抑えており、解決後の費用負担も軽くなります。